【2024年最新】360度評価とは?メリットとデメリット、導入時のポイントを紹介

【この記事でわかること】
・360度評価とは、同僚や部下など、あらゆる立場の人が評価を行う制度
・360度評価により客観的で公平な評価ができるようになる
・従業員自身が自分の改善点や持っている能力に気づきやすくなる
360度評価とは

360度評価とは、従業員の評価をより多面的なものにする手法です。従来の評価方法とは異なり、上司からの評価だけではなく、同僚、部下、他の部署の社員など、評価対象者に関わるあらゆる立場の人が評価を行うことが特徴です。
「360度評価」のほかに、「360度調査」「多面評価」「360度サーベイ」などと呼ばれ、英語では「360-degree feedback」と呼ばれています。
360度評価は複数の視点から従業員を評価することで、より客観的で公平な評価が可能になります。上司からの評価だけでは特定の視点や偏った評価が生まれやすく、従業員自身や他の関係者にとって納得しにくい場合があるためです。
しかし、360度評価では異なる視点からの評価が組み合わさるため、より客観的な結果が得られます。
メリットの多い評価方法ですが、実施するためには体制づくりが必要であることや、管理コストも発生します。紙やExcelを使用した手作業での管理だと時間と労力を膨大に必要とするため、360度評価システムの導入や効率化が重要です。
適切なツールを活用し、評価プロセスをスムーズにすることで、360度評価のメリットを最大限に活かすことができます。
360度評価の基礎知識を、下記で詳しく解説していきます。
【360度評価導入前の基礎知識】
・360度評価が注目される背景
・360度評価を導入する目的
・360度評価システムで効果的な運用ができる
360度評価が注目される背景
現代社会は絶え間なく変化している時代であり、この動きの中心には「VUCA」という言葉があります。VUCAは、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字をとったもので、現代社会を表している言葉です。
多くの企業や組織がこの変動の中でどのように適応していくかを模索しています。特に注目されているのが、どうやって従業員の業績や貢献を評価し、適切な評価をするかという点です。
元々、企業内での評価は上司の主観に大きく依存していました。しかし、近年の働き方の変化、特にテレワークやリモートワークの拡大により、これまでの評価方法では適切な評価が難しくなってきました。
そんな中、注目を集めているのが360度評価です。一人の上司の意見だけではなく、周りの多くの人、例えば部下や同僚からの意見や評価を取り入れることで、より全体的で公正な評価が可能になります。これまでは年功序列や上司との人間関係が評価の大きな要因となっていましたが、現代社会ではそのような主観的な評価ではなく、公平性や客観性が求められています。
さらに、現代の働き方や組織の構造が複雑化してきており、一方的な評価が難しい現状があるため、多面的な視点からの評価が求められています。このような背景から、360度評価は今、多くの企業や組織で注目されているのです。
これからの時代、企業や組織がさらなる成長や発展を遂げるためには、公平で客観的な評価方法の導入は欠かせない要素となります。
シーベースで独自に調査した360度評価に関するアンケートデータから、下記の通り導入率は全体で6割弱となっており、従業員が多いほど導入率は高まり、5,000名以上の企業では66%が導入済みです。

大企業ほど人材個々の状況が見えにくいため、360度評価を組み込んで可視化していると考えられます。
360度評価を導入する目的
360度評価の主な目的は、多面的な視点からの公正な評価を行うことです。一般的に考えられる評価制度というと、上司が部下を一方的に評価する形が多いですが、こういったシンプルな評価方法では、上司の主観や偏見、または上司と部下の関係性など、さまざまな要因によって評価が左右されてしまうことが考えられます。
たとえば、部下としては業務における能力は高いのに、上司との関係性が薄いと不当に低い評価を受けることもあれば、逆に関係性が深いと過度に高い評価を受ける可能性もあります。
また、一部のスキルや才能に目を向けがちで、他の大切な点を見落とすリスクもあります。このような偏った評価を避けるために、360度評価は上司だけでなく、同僚や部下、場合によっては外部の関係者からも評価を収集し、評価対象者をしっかりと把握することができます。
ただし、360度評価を適切に実施するためには、評価の目的を明確にする必要があります。評価の主な目的が「人事評価」であるのか、「人材育成」であるのかによって、評価の取り組み方やフィードバックの方法が変わってきます。
360度評価を導入する目的は企業によって異なりますが、基本的には人材育成や組織活性化を目的としていることが多く、直接給与に反映させるケースは少なくなっています。例えば、もし360度評価の結果が給与アップや賞与の査定に直結すると、評価者は率直な評価をしにくくなってしまいます。
また、シーベースでは、360度評価を導入している企業の人事担当者241名に「360度評価の実施で満足している点」を聞き、ランキングにしました。

実際の導入企業では、従業員のパフォーマンス向上や、部署間や異なる立場でのコミュニケーションの活性化など、360度評価が企業内での様々な組織課題に対して効果的であることがわかります。
360度評価システムで効果的な運用ができる
360度評価では評価者となる社員の数が増えるため、アンケートの作成や回収、結果の集計など、評価に関する事務作業が膨大になります。
具体的には、Excelで評価を管理しようとすると、シートが増えデータが分散して管理が大変になることが考えられます。
そこで、360度評価の運用を効率的に行うために必要なのが、360度評価システムです。
360度評価システムを利用することで、アンケートの配布や回収を自動化でき、集計結果も自動的にレポートを作成することが可能です。管理者の事務作業を大幅に軽減できるため、360度評価の運用に最適なツールとなります。
また、システム上で評価データを一元管理できるので、評価結果を人事考課や社員教育に活用しやすくなります。360度評価の目的の1つである「人材育成」につなげることができるのです。
360度評価のメリット
360度評価は、上司だけでなく、同僚や部下、時には顧客からの意見も取り入れることで、従業員の活かしきれていない能力や改善点が明確になるだけではなく、従業員のエンゲージメント向上や人間関係の問題解決にも役立つというメリットがあります。
360度評価を導入することによる下記のメリットを、それぞれ詳しく解説していきます。
【360度評価のメリット】
・客観的で公平な評価が可能になる
・改善点や活かしきれていない能力に気づくことができる
・従業員のエンゲージメントを向上させることができる
・上司からの評価だけを気にする必要がなくなる
・パワハラなど職場の人間関係の問題が見つけやすくなる
・管理職の育成に効果的
客観的で公平な評価が可能になる
360度評価は多方面からのフィードバックを取り入れるため、客観的な評価が可能となります。
これまでの評価方法は、大きく上司の主観が色濃く反映されることが多くありました。そのため、従業員としては自分がどのように評価されているのか、不明確で不安に感じることも少なくありませんでした。
360度評価が有効なのは、従業員が公平な評価を受けることができ、自分自身の成長やモチベーション向上に繋がるからです。これは企業にとっても大きなメリットとなります。公平な評価がされることで、社員の能力やスキルを正しく認識し、正しい場所で活躍させることができるようになります。
改善点や活かしきれていない能力に気づくことができる
360度評価の導入により、従業員自身の成長の手がかりを発見することが可能になります。
360度評価では上司だけでなく同僚や部下、時には顧客からの評価も取り入れるため、自分の改善点や持っている能力に気づきやすく、それを活かす方向でキャリアを考え直すきっかけになります。
また、自分で自己評価を行った結果と他者からの評価が大きく異なることもあります。このギャップを知ることで、自分の認識のズレを矯正して、より客観的な自己理解ができるようになります。
これは企業側のメリットでもあり、従業員の意外な能力や改善点を発見し、それをもとに新しい人材育成の取り組みや方針を考えることができます。
従業員のエンゲージメントを向上させることができる
企業や仕事への熱意など、従業員のエンゲージメントを向上させることができます。
360度評価によってポジティブな意見を受けることによって、自分の職場やチームメンバーに対する信頼が深まるようになります。
さらに、自分自身が評価する立場としても参加できるため、従業員は「自分の思いや感じたことが、しっかりと会社に伝わっている」という実感を得ることができます。
こういったエンゲージメントの向上は、企業全体の生産性を高めたり、従業員のスキルアップやチームの連携をより強くする効果があります。さらに、良好な職場環境が作られるようになるため、結果として従業員の退職を防ぐ役割も果たします。
上司からの評価だけを気にする必要がなくなる
これまでの人事評価は、多くが上司による一方的な評価でした。その結果、上司が良ければそれで良しという、多少偏った状況が生まれがちとなっていました。これにより、「上司の気持ちや意向だけを重視する」ような姿勢を持つ社員が多くなってしまいます。
そのような状況を解決するための手段として360度評価が役に立ち、評価の視点が上司だけでなく、同僚や部下、他部署の人、さらには外部の顧客まで、さまざまな角度からの意見や評価が取り入れられます。
つまり、360度評価であれば「多角的な視点」からの評価を受けられるため、公平性が大きく向上します。社員一人ひとりが様々な人からフィードバックを受けることで、自分自身の役割や責任についての認識が深まります。
パワハラなど職場の人間関係の問題が見つけやすくなる
360度評価によって、パワーハラスメントなど職場のさまざまな人間関係の中で起きる問題をすぐに見つけることができます。360度評価は多くの人からの評価を集めるため、これまでの評価方法では見落とされがちな部分もしっかりと評価することができるためです。
例えば、Aさんが部署内で少数派の意見を持っていて、それが多数派の意見と異なるためにいじめの対象になっていたとします。これまでの上司だけの評価では、このような問題は見落とされる可能性が高いですが、360度評価の場合、部下や同僚からのフィードバックによりAさんの状況が明らかになり、すぐに対策を打つことができます。
管理職の育成に効果的
360度評価は管理職の育成に対しても効果的です。管理職が自身の行動やマネジメント手法を、同僚、上司、部下といった様々な視点から評価されることにより、自分の強みや改善点を客観的に把握し、その結果をもとに改善策を立てることができるためです。
管理職は組織の中で重要な役割を担い、チームや部署のパフォーマンスを大きく左右する存在であるため、管理職が成長することは会社全体の成長に繋がります。360度評価を利用することで、管理職は自身の行動や業務へのアプローチを様々な視点から見直し、客観的な自己分析を行うことができます。
これにより、主観的な認識と他人からの認識とのギャップが明確になり、その差を埋めるための行動ができるようになります。
360度評価をされた管理職には、フィードバックが非常に重要です。フィードバックを受けることで具体的な改善策を立てやすくなり、自身の行動やマネジメント手法を改善するきっかけとなります。
また、上司と部下の間の信頼関係の構築にも影響します。360度評価を通じて部下からの評価を受けることで、上司は部下がどういった見方をしているのかを把握することができ、今後はより効果的なコミュニケーションが取れるようになります。
360度評価を実施するには、評価ポイントを明確にし、管理職特有の役割に対する評価を適切に行う必要があります。
リーダーシップやメンバーの育成能力、マネジメントスキルなど、管理職に求められる具体的な能力に焦点を当てた評価を行う必要があります。さらに、フィードバックは具体的に行い、評価された管理職が明確な改善策を実施できるように360度評価を設計することも重要です。
360度評価のデメリット
360度評価にはメリットだけでなく、いくつかのデメリットや欠点も存在します。特に導入初期や運用段階においては、従業員の混乱や評価のズレ、コストの増加など様々な課題が出てくることが予想されます。
また、従業員一人ひとりの評価スキルや意識、上司と部下のコミュニケーション不足、さらには組織内の人間関係まで、360度評価を上手く活用するためには課題も知っておく必要があります。
導入を検討する際には十分な準備が必要です。主に下記のような360度評価のデメリットに焦点を当て、具体的な問題点とその対策方法について詳しく解説していきます。
【360度評価のデメリット】
・導入から運用まで時間や労力が必要
・評価に慣れていない従業員が評価を行うことは難しい
・上司の指導が甘くなってしまう可能性がある
導入から運用まで時間や労力が必要
多くの人が評価に関わることはデメリットにもなり得ます。
各従業員が多くの評価を行う必要があり、多くの時間や労力を必要とします。たとえば、ある部署のAさんを評価するとき、同僚はもちろん、上司や他部署の人までが評価することになるため、評価を集め最終的にまとめるまでの過程はかなりの時間とコストがかかるのです。
さらに、360度評価を正しく実施するためには、人事や専門のチームが導入背景や運用手順などをしっかりと全従業員に伝える必要があります。フィードバックシートの適切な使用方法や、どのように客観的な評価を行うかなど、具体的な案内が必要となります。
導入の初期段階では、360度評価に従業員が慣れるまでの期間や、明確な評価基準を定めるための教育などのコストが発生します。さらに、運用を始めてからも、その運用方法を改良し、より質の高い評価を行うためのPDCAサイクルの実施や、プロジェクトの進行管理など継続的な取り組みが必要です。
評価に慣れていない従業員が評価を行うことは難しい
多くの従業員が「評価を行う」という新たな役割を担うことになりますが、これは簡単なことではありません。というのも、評価を行う上での自分自身の感情や、偏見を全て無くすことは難しいからです。
その結果、親しい同僚や不仲な関係の同僚、さらにはあまり知らない人への評価が事実よりも主観に基づいたものとなるリスクが高まります。
さらに、評価のスキルや経験を持たない多くの従業員が評価に関わることで、その評価がどれだけ客観的であるのか、公平性が保たれているのかという点が疑問視されます。
匿名での評価が行われますが、評価者が誰であるかを被評価者が推測することも考えられます。その結果として正直な意見が伝わらない、あるいは遠慮がちな評価がされてしまうことも無視できません。
加えて、お互い良い評価をするための事前の打ち合わせ、いわゆる「根回し」を行う従業員が現れることも予測されます。このような行動が増えると、360度評価が目指す理想的なフィードバックを得る目的が損なわれてしまいます。
評価の公平性や客観性を確保するための取り組みが360度評価の導入には必要で、従業員一人ひとりの意識向上や教育の徹底を意識する必要があります。
上司の指導が甘くなってしまう可能性がある
上司が部下からの評価を過度に意識し、その結果、指導が甘くなってしまう場合があります。
従業員は、自分の直接の上司の業務内容全てや背景などを完全には把握していないことが多いです。そのため、上司が部下のために厳しい指導を行っても、その背景や目的が部下に十分に伝わらなければ、単に「厳しい上司」という印象を持たれる恐れがあります。
このような状況が続くと、上司自身が「部下からの評価が低くなるのでは?」という危機感から、指導を控えめにする、もしくはその指導自体を避けるようになる可能性が考えられます。
指導の質が低下することは、長期的に見れば組織の成長やその中で働く従業員たちのスキルアップを妨げることに繋がります。
この問題を解消するためには、部下が上司を評価する際の項目の精査や、上司と部下の間のコミュニケーションをさらに充実させることが必要です。具体的には、評価の項目を明確にすることで、部下が上司の業務内容や背景を理解しやすくするとともに、上司と部下の間での意見交換やフィードバックの機会を増やすことで、お互いの理解を深める取り組みが必要です。
360度評価を導入する時のポイント
360度評価を実施する際にはいくつかのポイントと注意点があり、意識せずに進めると360度評価の導入効果は半減してしまいます。
効果を最大限に発揮するためには、その目的や運用計画を明確にすることや、従業員との共有が欠かせません。
下記のポイントについて、詳しくご紹介します。
【360度評価導入のポイント】
・導入目的や運用計画を明確にして従業員と共有する
・評価基準を統一する
・評価後に適切なフォローアップを行う
・設問数を過剰に多く設定しない
・フィードバックと合わせて改善策を伝える
導入目的や運用計画を明確にして従業員と共有する
どのように360度評価を活用するかということを、導入前から具体的に計画を立てておくことが重要です。
目的を明確にすることで、360度評価が期待通りに機能しているかどうかを後々検証する際に、客観的な基準で判断がしやすくなります。
仮に目的が曖昧な状態で導入を進めた場合、360度評価の効果検証が困難になるだけでなく、結果が期待したものとかけ離れてしまう可能性があります。さらに、360度評価システムを導入する理由を従業員にしっかりと説明できない場合、従業員の協力を得ることが難しくなります。
360度評価の導入と運用を成功させるためには、従業員が360度評価の導入目的を理解し、自発的に評価への取り組みに参加することが重要です。
そのため、導入から最大の効果を引き出すためには、計画段階から実行に至るまでの一連の流れを、すべての従業員と共有する必要があります。導入の意図と目的を社員全員が理解し、共感することで、360度評価システムはただの形式的なものではなく成果に結びつく効果的な仕組みになります。
評価基準を統一する
従業員が違和感なく360度評価を受け入れ、日常業務に落とし込めるような環境をつくることが重要です。そのためには、360度評価での評価方法をしっかりと定め、それを従業員一人ひとりが把握し、理解する必要があります。
評価基準が統一されていなければ評価者によって意見が分かれ、不公平な結果が生まれる原因になり得ます。特に360度評価の場合、通常は評価側に回ることのない社員も評価者として参加することになります。
これまで評価を行ったことがない社員にとっては未知の領域ですので、不安を感じることなく、公平に評価に加わるためにも、分かりやすい評価基準が必要となります。
公平な評価を進めるためには、評価者が自分自身の意見を匿名で述べられるようにすることも必要です。これにより、誰の意見かを判別することなく本音のフィードバックを行うことができるようになります。
評価後に適切なフォローアップを行う
評価が完了した後の適切なフォローアップも重要です。評価シートを回収しただけでは、その効果を最大限に活かすことはできません。
360度評価は、収集した評価をもとにした具体的な行動の改善までを行う必要があります。360度評価を行う側は、自分が行ったフィードバックが実際になんらかの形で良い変化に繋がることを望んでいます。
そのため、もし評価者がフィードバックが単なる形式的なものに過ぎないと感じれば、今後360度評価の積極的なフィードバックを行わないようになってしまうかもしれません。
評価結果の分析を終えた後は、個々の被評価者と向き合う時間をつくりましょう。この個別面談では、改善が必要とされる部分について話をすることはもちろん、評価者たちから高い評価をもらっているポイントについても具体的に伝えましょう。
一方的に欠点のみを指摘してしまうと、被評価者はネガティブな感情を持ってしまうためそれが仕事に対する熱意を削ぐだけでなく、360度評価への協力意欲を無くすことに繋がります。
加えて、360度評価が設定した目標に対して成果を上げているかを常に確認し、改善の余地があればPDCAサイクルを活用して改善を進めていきましょう。
設問数を過剰に多く設定しない
設問数を適切に設定することも、360度評価では重要です。
設問数が過剰に多い場合、従業員が評価にかける時間と労力が増えてしまい、結果として業務効率に悪い影響を与えてしまう可能性があります。360度評価の作業が、本来の業務で使うべき時間を奪ってしまうのです。
また、設問が多すぎるとそれぞれの設問を深く考えることがなくなり、結果として360度評価の質が低下してしまうことが懸念されます。各設問に対して浅い回答になると評価は表面的なものとなり、360度評価の目的であるフィードバックの効果を得ることが難しくなります。
そのため、設問数を適切に設定することは評価作業を効率化させるだけでなく、評価の質を高めるためにも重要です。
設問数は最低限に留め、各設問が特定の評価目的に沿っていることを確認しましょう。最低限の設問には、評価される従業員の職務内容や能力、役割等を踏まえ、関連性の高い設問を選定することが重要です。
最終的には、設問数を適切に管理することによって、360度評価の作業が従業員の業務効率やモチベーションに与える悪影響を最小限に抑え、同時に評価の精度を高めることができます。
フィードバックと合わせて改善策を伝える
360度評価では、フィードバックと共に改善策を提示することが重要です。
フィードバックによって得られた評価の内容は、具体的な改善行動に移すためのきっかけになると同時に、従業員が自分の成長の方向性を決める上での重要な情報となります。具体的な改善策を提示することにより、フィードバックが活かされます。
例えば、360度評価で従業員が「協調性が低い」というフィードバックを受けた場合、ただその点を伝えるだけでは、その従業員は自分がどのように行動を改めれば良いのか具体的なイメージを持ちにくいでしょう。
しかし、「プロジェクトチーム内で意見が異なる同僚の提案にも耳を傾け、積極的に議論に参加する」などの改善策を同時に提示することで、具体的な行動目標が明確になります。これにより、従業員は行動を見直し、実際にコミュニケーションが改善されるように行動することができます。
また、改善策を提示することで、フィードバックがネガティブな内容であっても、それをポジティブに成長できる機会と捉えることができます。
360度評価の導入事例

360度評価は、多面的な視点から社員のパフォーマンスを測り、職場でのコミュニケーションの質を高めるために、多くの企業に採用されています。
その導入事例は様々で、各社の具体的な状況に合わせた運用が行われています。
ここでは、シーベースが提供している「CBASE 360°」の異なる業界での下記企業の実践的な導入事例を通じて、360度評価が企業文化や組織運営にどのような影響を与えているのかを掘り下げていきます。
【導入事例】
・株式会社ぐるなび
・株式会社マネーフォワード
株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなびでは、マネジメント力の向上と社員の気づきを促すために360度評価を導入しました。
2019年に初めて実施した後、コロナ禍の影響でPDCAサイクルを十分に回すことができず、2020年は実施せず、2021年に再び実施しました。この施策は、リモートワーク中心の働き方においてマネジメントがしっかりとできているかを確認する目的も兼ねています。
360度評価を導入した狙いは主に下記の通りです。
・本人が気づきを得ること
・行動変革を促すこと
・企業理念の実践度合いの確認
・社員の心理的安全性の確保
・働き方改革の推進
そして、施策を実施するうえで、下記のようなポイントを意識しているようです。
・企業理念に基づく役割定義を反映した設問を作成すること
・4段階評価へ変更すること
・回答者の匿名性を確保すること
・誹謗中傷を回避すること
・360度評価の内容を実用的に活用するために工夫すること
こういった工夫のもと、マネージャーたちは実際の気づきの機会を得て、行動改善が進んだと報告されています。360度評価の結果はPDFで配布され、各マネージャーが上司と個別に面談を行い、改善策を進めています。
今後ぐるなびでは同じ設問で継続的に360度評価を実施することで、マネジメントスキルを向上させることを目指しています。
マネジメントを可視化することや周囲の意見を聞くことが、社員の成長や企業の発展には重要としています
株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、企業成長に伴いマネジメント層の強化を重視しました。急速に増加した従業員数の中で、一人一人の能力向上が必要と判断していたためです。
特に、多くがマネジメント経験が未熟なメンバーや新しい文化に適応しなければならない中途採用者で構成されていたため、統一されたマネジメントスキルの向上が求められていました。
この課題に対応するため、リーダー向けの合宿が企画され、そのプログラムとして360度フィードバックが実施されました。
この合宿では、マネーフォワードの基盤となるMVVC(ミッション、ビジョン、バリュー、カルチャー)の深い理解などを目的としており、会社の創業理念や成長過程を共有するセッションから始まり、個々の課題を自己分析し、すぐに実行可能な行動計画を策定するワークショップで構成されていました。
合宿の際には、特に参加者が自分自身を見直すための工夫がなされました。360度フィードバックでは効果的なフィードバックを得るために、参加者自身が評価者を選ぶようにした点が挙げられます。
360度評価実施後のフィードバックでは、多くの参加者がこのプログラムを通じて新たな気付きがあったと報告しており、行動変容につながる具体的なアクションプランが立てられたと感じていました。
360度評価のまとめ
360度評価は従業員のパフォーマンスを多面的に評価する方法であり、その多面的なフィードバックが自己認識の改善に繋がります。
上司だけではなく、同僚や部下といった幅広い関係者から意見を集め評価することにより、従業員自身がまだ認識していない能力や改善点を明確にすることができます。
社員一人ひとりが自分自身の成長を実感し、組織全体の発展に繋がる行動をとるようになることは、組織にとっても大きなメリットです。特に、一般職員が管理職の評価を行うことで、自分が組織運営の一端を担っているという意識が高まります。
また、360度評価を実施する際に気になるのが、評価者が誰なのかバレてしまうのではないか、ということですが、ほとんどの場合、360度評価は匿名で行われるので、誰がどんな評価をしたかは分からず周囲にはバレることがない仕組みになっています。
シーベースの360度評価システム「CBASE 360°」を導入することで、従業員個々の成長はもちろんのこと、組織全体を成長させることができるため、戦略的な人材マネジメントのため導入を検討してみてはいかがでしょうか。

「CBASE 360°」は、株式会社シーベースが提供するHRクラウドシステムです。経営を導く戦略人事を目指す人事向けのお役立ち情報をコラムでご紹介します。


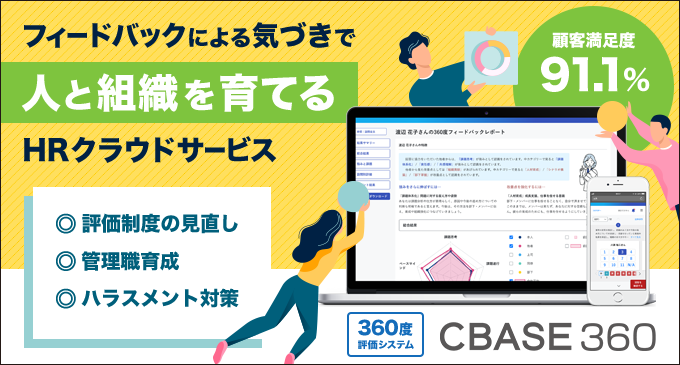




![[記事内]サイド上部バナー(マンガでわかる360)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/cbase360_banner576x480.png)





![[記事内]サイド中部バナー(セミナー)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/banner_seminar01_290x160.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:360)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/BN_manga_B.png)